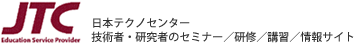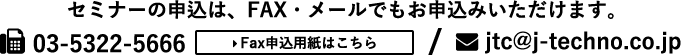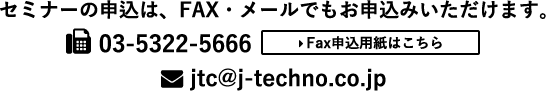研究開発における生成AIおよびAIエージェントの効果的な活用法と非構造データのAI分析および最新技術 <オンラインセミナー>
~ 研究現場における生成AIの最新動向、論文、実験ノート、技術資料など非構造データのAI分析と活用法、AIエージェント構築とMCP・A2Aの技術的活用 ~
・研究プロセス全体にインパクトを与える生成AIの応用可能性と最新技術を修得し、研究開発の飛躍的効率化に応用するための講座
・Azure OpenAI や MCP(Model Context Protocol)などの最新技術から実験ノートや報告書をAIに扱わせるためのデータ整備とナレッジ抽出および戦略立案や新テーマ選定への活かし方まで実践的に学び、研究の質・スピード・創造性を向上させよう!
オンラインセミナーの詳細はこちら:
・WEB会議システムの使い方がご不明の方は弊社でご説明いたしますのでお気軽にご相談ください。
講師の言葉
製造業や研究開発の現場において、AI・クラウド・データを実業務に落とし込むDX推進を多数実践してきた技術者が登壇します。マテリアルズインフォマティクスや研究支援システムの構築を専門とし、国家プロジェクトや企業現場での導入支援において、「科学とITの橋渡し役」として高い実績を持ちます。
本セミナーでは、注目を集める生成AIを“業務支援ツール”にとどめず、非構造データの活用、AIエージェント構築、ナレッジ循環の仕組み化といった視点から、「使われ続ける研究支援システム」の設計と定着戦略を解説します。
Azure OpenAI や MCP(Model Context Protocol)などの最新技術を活用した構成や実例紹介も交えつつ、研究DXに取り組むエンジニア、マネージャー、IT企画担当者が明日から実践できる知見をお届けします。
セミナー詳細
| 開催日時 |
- 2025年12月05日(金) 10:30 ~ 17:30
|
| 開催場所 |
オンラインセミナー |
| カテゴリー |
オンラインセミナー、ソフト・データ・画像・デザイン |
| 受講対象者 |
・製造業、化学、素材の研究開発担当者
・マテリアルズインフォマティクス/プロセスインフォマティクス推進者
・R&D部門のDX推進・IT企画担当者
・生成AI・Azure OpenAI の業務適用を検討している方
・研究開発におけるAI導入の方向性を掴みたいマネージャー・技術戦略担当者
・サイエンスとクラウドの両方の視点からDXを進めたいと考えている方
・データ・AI・業務がうまく連携できていないと感じている方
・MCP(Model Context Protocol)やA2A(Agent to Agent)など、次世代のAIエージェント技術の研究DXへの応用に関心がある方 |
| 予備知識 |
・特に必要ありません |
| 修得知識 |
・研究開発分野における生成AIの最新トレンドと、実務への活用手法を把握できる
・Azure AI Services や OpenAI を活用したシステム構築の基本設計が理解できる
・AIエージェントや自律型AIといった次世代技術の方向性と応用事例に触れられる
・論文、実験ノート、技術資料など非構造データのAI分析のアプローチを学べる
・組織内における研究ナレッジの共有・活用を促進するAI導入の進め方を整理できる
・論文・特許・業界ニュースを用いたトレンド分析の仕組みと応用の視点を得られる
・データ整備、業務巻き込み、倫理的配慮など導入時に直面する課題とその対処法を理解できる
・「生成AI × データ × プラットフォーム」の観点から、研究の質・スピード・創造性を高める手法を習得できる
・MCP(Model Context Protocol)や A2A(Agent to Agent)を活用したAIエージェント設計の基本構造を把握し、ツール・データベースとの連携イメージを持てる
・MCP や A2A などの次世代 AI エージェントを材料探索・プロセス最適化に導入した具体的な事例や状況を把握できる
・サイエンスとクラウド双方の視点から、研究支援システムの設計方針を考える力が養える
・「データはある」「AIもある」「でもつながらない」といった現場のリアルな課題に対する構造的な解決策のヒントを得られる |
| プログラム |
1.研究現場における生成AIの最新動向と導入課題
(1).研究DXが進まない根本原因と“PoC止まり”の実態
・研究現場で生成AIやDXが注目される一方、PoCで止まってしまう例が後を絶ちません。なぜ“使われないシステム”になるのか、技術的課題だけでなく、業務・文化・マネジメント面の背景を整理します。
(2).生成AIによる変革ポテンシャルと活用の方向性
・文書作成・情報検索といった単純活用を超え、研究プロセス全体にインパクトを与える生成AIの応用可能性を示し、以降の章でその実装戦略を展開します。
2.生成AIの構成と活用:Azure OpenAIとLangChainの基本
(1).Azure AI Services・OpenAIの特徴と構成パターン
・Azure OpenAI や Azure AI Services (Cognitive Services) の技術概要を整理し、企業内で活用されているシステム構成例(セキュリティ対応含む)を分かりやすく紹介します。
(2).LangChainやRAGによる企業内生成AIの実装例
・データベース連携やドキュメント検索に用いられる LangChain やRetrieval-Augmented Generation(RAG)構成を活用し、社内ナレッジBotなどへの展開例を紹介します。
3.非構造データ(論文・ノート・レポートなど)の活用手法
(1).実験ノートや報告書をAIに扱わせるためのデータ整備
・研究現場に眠る PDFやWordファイル、手書きノートといった非構造データをAIに読み取らせるための、構造化やメタデータ整備の設計手法を解説します。
(2).RAG構成による自然言語ナレッジ抽出の実践
・ドキュメントをベースに生成AIが高度な知識応答や要約を行う仕組みを紹介。
自然言語での再利用を可能にする知識抽出の実践手法を紹介します。
4.AIエージェント構築とMCP・A2Aの技術的活用
(1).Model Context Protocol(MCP)とAgent to Agent(A2A)の基本概念
・生成AIを“指示を受けて答える存在”から“状況を理解し、行動する存在”へ進化させるための重要技術、MCPとA2Aの役割と仕組みを解説します。
(2).業務ツール・データベースとの連携による“行動するAI”の設計方法
・AIがツール操作やDB参照などを自律的に行う「AIエージェント」の設計例を、実際のAzure構成やユースケースに基づいて紹介します。
5.論文・特許・ニュースを活用したトレンド分析と戦略活用
(1).文献・情報源の自動要約・分類・可視化の仕組み
・生成AIを活用して技術文献や特許、業界ニュースを読み取り、関連性・カテゴリ分類・トレンド可視化を自動化する構成を紹介します。
(2).技術動向の把握から研究テーマ・開発方針の立案へ
・得られた知見をもとに、どのように戦略立案や新テーマ選定に活かすか。研究戦略や製品開発を支える知識活用の考え方を提示します。
6.マテリアルズインフォマティクス(MI)/プロセスインフォマティクス(PI)との融合事例
(1).MI/PI領域における生成AIの具体的応用事例
・マテリアルズ・インフォマティクス(MI)やプロセスインフォマティクス(PI)分野における生成AIの活用事例(材料探索、異常検知など)を紹介します。
(2).材料特性予測、製造条件最適化のクラウド構成例
・Azure OpenAIやMCP・A2Aを自社データと連携させて実現する、材料特性予測および工程最適化のクラウド構成例を示し、その効果、限界、ならびに実装時の注意点について整理します。
7.“使われ続けるAI”の条件と定着戦略
(1).導入して終わらせないための業務巻き込み・教育設計
・PoCで満足せず、継続活用につなげるために必要な「巻き込み設計」や「ユーザー教育」の具体例を提示します。
(2).PoC後の評価・改善・継続利用に向けた設計ポイント
・活用状況の可視化、KPI設計、改善ループの確立など、AI定着を支える運用設計の実務的なポイントを解説します。
8.生成AI×研究DXの未来像と導入で押さえるべき視点
(1).AIと人の役割分担:創造性と判断力を支える設計論
・AIによる自動処理と、人間による判断・仮説構築のバランスを考え、どこまで任せるか・残すかの方針を整理します。
(2).研究・開発組織における生成AI活用の中長期ビジョン
・2026年以降の技術トレンドを見据え、今、どのような仕組み・人材・データ設計をしておくべきかを考察します。
|
| キーワード |
PoC Azure AI Services・OpenAI LangChain RAG 社内ナレッジBot 非構造データ 自然言語ナレッジ抽出 AIエージェント MCP A2A トレンド分析 マテリアルズインフォマティクス(MI) プロセスインフォマティクス(PI) 製造条件最適化 教育設計
|
| タグ |
AI・機械学習、ヒューマンスキル、企画書・提案書、教育、研究開発、商品開発、人材育成、問題解決・アイデア発想、ソフト教育、データ解析、材料、統計・データ |
| 受講料 |
一般 (1名):49,500円(税込)
同時複数申込の場合(1名):44,000円(税込)
|
| 会場 |
オンラインセミナー
本セミナーは、Web会議システムを使用したオンラインセミナーとして開催します。
|
こちらのセミナーは受付を終了しました。
次回開催のお知らせや、類似セミナーに関する情報を希望される方は、以下よりお問合せ下さい。