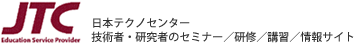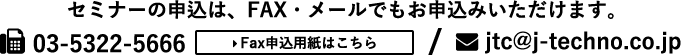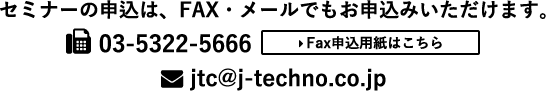効果的なデザインレビューの実践と生成AIを活用した未然防止への応用実践講座 <オンラインセミナー>
~ AIを活用した故障要因の体系的な洗い出しと「見える化」、データに基づいた実効性の高い対策立案、再現性の高い問題解決能力の養成、組織的な未然防止文化の醸成 ~
・生成AIを活用して膨大な技術情報を効率的に分析し、人間では見落としがちなリスクを可視化して、製品の品質確保に活かすための講座
・属人的なスキルに依存しない効果的なデザインレビュー方法を実践的に修得して、従来のレビューでは困難であったリスクの発見に応用しよう!
オンラインセミナーの詳細はこちら:
・WEB会議システムの使い方がご不明の方は弊社でご説明いたしますのでお気軽にご相談ください。
講師の言葉
なぜ今、デザインレビュー、未然防止に「生成AI」が必要なのか?
製品開発の複雑化は、部門や企業の垣根を越えた「隠れた問題のつながり」を生み出し、従来の人の目によるレビューだけではリスクの発見が困難になっています。
本セミナーでは、生成AIを活用して膨大な技術情報を効率的に分析し、人間では見落としがちなリスクを可視化します。これにより、属人的なスキルに依存しない、データドリブンで効果的なデザインレビューを実現。開発のフロントローディング(前倒し)を加速させるための具体的な手法を、実践的なステップで学習します。
セミナー詳細
| 開催日時 |
- 2026年03月18日(水) 10:00 ~ 17:00
|
| 開催場所 |
オンラインセミナー |
| カテゴリー |
オンラインセミナー、品質・生産管理・ コスト・安全 |
| 受講対象者 |
・製品や部品の開発、設計、品質保証などに携わる方
(自動車部品、電子機器・部品、機械製品、医療機器、その他製品) |
| 予備知識 |
・AIツールや生成AIに関する専門知識は不要ですが、「Google NotebookLM」とChatGPTなど一般AI(何れも無償版で可)をPCにインストールしてソースの入れ方と質問の出し方になじんでください |
| 修得知識 |
・製品全体を俯瞰し、客観的に影響を捉える視点
・AIを活用した、抜け・漏れのない影響分析スキル
・マトリクス思考による問題構造の整理手法
・AIを活用した故障要因の体系的な洗い出しと、デザインレビューの実践手法
・データに基づいた実効性の高い対策を立案するスキル
・関係部門を巻き込み、円滑に合意形成を行うためのデザインレビュー手法
・再現性の高い問題解決能力の養成:属人的な経験や勘に頼らず、データに基づいた再現性のある問題発見・解決能力
・開発効率と品質の向上: 設計初期段階での手戻りを大幅に削減し、品質向上と開発リードタイム短縮を両立
・組織的な未然防止文化の醸成: 部門横断で課題を共有し、組織全体で未然防止に取り組む文化が醸成され、部門間の連携が円滑になる |
| プログラム |
1.デザインレビューの実施方法とポイント
(1).一般的なデザインレビューの段階
a.設計内の技術議論
・設計部門内での構想・仕様・設計妥当性の検討
b.設計とそれ以外の社内との変化点確認
・他部門と連携し、設計変更・新規設計が社内全体に及ぼす影響(変化点)を確認
c.製品開発監査
・開発全体の進捗や設計プロセスの遵守を確認する
(2).デザインレビューの実施時期・内容
【構造決定前の問題発見のデザインレビュー】
時期:構造変更ができなくなる前の段階で実施
a.構造理解と分析
・対象製品の構造を理解
・各構成部品の役割・性能を把握
・故障モードの理解
・故障モードの原因(変化点)の理解
b.設計との議論
・故障モードや原因(変化点)の抜けを確認し、設計に提案
・従来内容で対応可能な項目
・自部署に変更が伴う項目
・自部署で対応できない項目 → 設計変更を議論
c.全体確認:この構造で開発を進めてよいかを判断
【生産準備前の問題解決のデザインレビュー】
時期:設計図面がフィックスし、生産準備が開始される前に実施
a.設計との調整
・自部署に変更が伴う実施内容を設計に説明
・自部署では対応できない項目について、設計変更を含めて対応確認
b.全体確認
・全部署での対応内容を共有し、全体として問題がないかを確認
・最終的に、この対応方針で生産へ進めることが妥当かを判断
2.AIを活用したデザインレビューの実践手法と未然防止のポイント
(1).AIによる影響範囲の網羅的な「見える化」
a.設計変更の背景や目的のAIへ入力
b.関連する機能や使用条件の変化点のリストアップ
c.過去のデータ(構成部品、工程など)から影響範囲の変化点を抽出
d.影響を受ける機能や性能を整理し、レポート化
e.AIの分析結果を確認・調整
(2).AIを活用した潜在リスクの「問題発見」
a.変更箇所と機能をマトリクス化し、各交点の重要度を可視化
b.マトリクスの重要度を確認・修正
c.各交点における故障モード(FMEAの考え方を応用)を抽出
d.抽出された故障モードの妥当性を確認
e.各故障モードの潜在的な原因を網羅的にリストアップ
f.原因を部門・企業ごとに関連付けて整理し、レビュー資料を自動作成
(3).AIによる最適解の導出と「問題解決」
a.過去の類似事例や技術情報から、有効な対策案を複数提案
b.AIの提案を基に、最適な対策を選定・具体化
c.対策実施に必要な関係部署の連携とタスクを整理
d.AIの整理結果を基に、具体的な対応内容を作成
e.標準化や横展開を見据えたデザインレビューの実施項目を提案
f.提案された項目を確認し、デザインレビューを実践
|
| キーワード |
見える化 潜在リスク 問題発見 故障モード FMEA 最適解 問題解決 デザインレビュー |
| タグ |
AI・機械学習、リスク管理、品質管理、未然防止、FMEA・FTA・DRBFM、設計・製図・CAD |
| 受講料 |
一般 (1名):49,500円(税込)
同時複数申込の場合(1名):44,000円(税込)
|
| 会場 |
オンラインセミナー
本セミナーは、Web会議システムを使用したオンラインセミナーとして開催します。
|