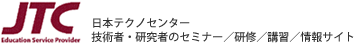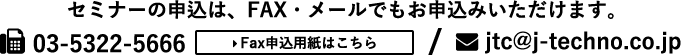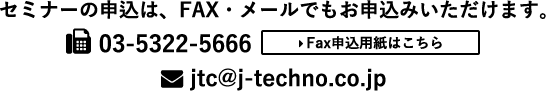車載システム開発における「システム設計」の基礎と実践のポイント:SysMLによる可視化技術と設計思想・構造・応用 <オンラインセミナー>
~ アーキテクチャ設計と構造設計、設計におけるトレーサビリティ整合性の確保、システム設計を支える可視化と構造化の技術、SysMLダイアグラムの体系と使用ポイント ~
・安全かつ高信頼が求められる車載システムで必要不可欠となる「システム設計」の実践ポイントを修得し、要件に適合した高品質なシステムを効率的に開発するための講座
・システム構造やつながりなどを記述するSysMLを使いこなすためのポイントを修得し、設計情報の整合・構造化・可視化を実現して、信頼性の高いシステム開発に活かそう!
・SysMLは複雑なシステム、特に組み込みシステムやハードウェアとソフトウェアが連携するシステムに対して効果的です。ハードウェア、ソフトウェア、ネットワークなど、異なるドメインを一つの統合された視点で捉え、設計を行うことができます。これにより、システム全体の調整がしやすくなります。また設計初期の段階からリスク要因を分析でき、改善策を講じることが出来たり、モデリング手法を使うことで、再利用性を向上させることができます。
オンラインセミナーの詳細はこちら:
・WEB会議システムの使い方がご不明の方は弊社でご説明いたしますのでお気軽にご相談ください。
講師の言葉
現代の車載システムは、機能の高度化・電子制御化・ネットワーク化が進む中で、従来の部品設計や機能単位の開発では対応が困難になっています。特にADASや自動運転など、安全かつ高信頼が求められる分野では、「システム設計」という視点での統合的なアプローチが不可欠です。
しかし多くの技術者にとって、「設計」はできても「システム設計」となると、粒度・範囲・考え方が違い、戸惑うケースが少なくありません。
本セミナーでは、SysMLの図の使い方だけでなく、それを支える設計思考、設計プロセスの筋道を重視します。設計情報の整合・構造化・可視化をどう実践に活かすかを、具体的な事例を通じて体感していただきます。
セミナー詳細
| 開催日時 |
- 2025年12月11日(木) 10:30 ~ 17:30
|
| 開催場所 |
オンラインセミナー |
| カテゴリー |
オンラインセミナー、ソフト・データ・画像・デザイン |
| 受講対象者 |
・自動車OEMおよびTier1のシステム設計担当者・開発エンジニアの方
・ADAS/自動運転領域の機能開発・構造設計に関わる技術者の方
・MBSEやSysMLの導入・活用を検討している開発リーダー・マネージャー
・MBDや車載ソフト開発に取り組んでおり、システム設計の視点を取り入れたい方
・SDV時代に向けた「全体設計力」を高めたい若手〜中堅技術者
・SysMLやシステムズエンジニアリングを基礎から学びたい初学者・未経験者 |
| 予備知識 |
・予備知識は必須ではありませんが、以下の分野に関する理解があると、より深い学びにつながります
・自動車業界の基礎知識(自動車システムの構成要素や電子制御システムの基本構造)
・ソフトウェア開発や制御工学の基礎知識(モデルベース開発(MBD)やCAEの概念)
・システム設計やシミュレーション技術の概要(SysML、Matlab/Simulink、Modelicaなど)
・製品開発プロセスの知識(要件定義、設計・検証プロセスに関する一般的な理解) |
| 修得知識 |
・「システム設計とは何か?」という根本的な考え方や背景について理解できる
・一般的な設計との違いや、システム設計で求められるスコープや思考の構造がわかる
・要求分析・ユースケース抽出・アーキテクチャ設計・インタフェース設計など、システム設計に必要なプロセスの全体像が掴める
・SysMLで使われる14種類のダイアグラムの体系や使いどころが理解でき、設計意図を“図で表現する力”の基本が身につく
・ADASなどの設計事例を通じて、設計判断や構造化・整合の実践的なアプローチを学べる
注意:※SysMLモデリングツールの操作実習は行いません
モデルや図の事例は、Excel等を用いて視覚的にわかりやすく解説します。 |
| プログラム |
1.なぜ今、システム設計なのか?
(1).なぜ今、システム設計なのか?
(2).自動車開発を取り巻く変化と複雑化
(3).部品思考からシステム思考への転換
(4).従来手法の限界と設計思考の必要性
2.システム設計とは何か?
(1).設計とシステム設計の目的とスコープの違い
(2).システム設計で扱う対象と特徴的な課題
(3).システム設計とMBSEの関係性
(4).設計力として求められる思考の構造化とは
3.システム設計の進め方(プロセス編)
(1).システム設計における基本の流れとは?
(2).「要求」とは何か?「仕様」とどう違うのか?
(3).ユースケース起点の設計思考
(4).アーキテクチャ設計と構造設計
(5).インターフェース設計とシステム構成の整合
(6).設計におけるトレーサビリティ整合性の確保
4.システム設計を支える可視化と構造化の技術(SysML編)とそのポイント
(1).モデルで支えるシステム設計:なぜ可視化が必要か?
(2).SysMLとは何か?:MBSEにおける標準言語の役割
(3).SysML全14種ダイアグラムの体系と使うポイント
(4).要求分析とユースケース定義
a.要求図
b.ステークホルダ図
c.ユースーケース図
(5).振る舞いを捉える図の活用
a.アクティビティ図
b.シーケンス図
c.状態遷移図
(6).構造を可視化する図の使い分け
a.ブロック定義図
b.内部ブロック図
(7).数式と条件のモデル化
a.パラメトリック図
(8).モデルの管理と構成設計
a.パッケージ図
(9).トレーサビリティの実装と全体統合
5.事例で学ぶ設計のポイント(実践編)
(1).設計事例1:ACC(アダプティブクルーズコントロール)のシステム設計
(2).設計事例2:車線維持支援システム(レーンキープアシスト)のシステム設計
6.質疑応答とまとめ
|
| キーワード |
システム設計 スコープ MBSE ユースケース アーキテクチャ設計 トレーサビリティ整合性 SysML ダイアグラム 要求分析 ユースケース定義 モデル化 |
| タグ |
ソフト管理、ソフト品質、ソフト教育、デバイスドライバ、組み込みソフト、自動車・輸送機、車載機器・部品、電装品 |
| 受講料 |
一般 (1名):49,500円(税込)
同時複数申込の場合(1名):44,000円(税込)
|
| 会場 |
オンラインセミナー
本セミナーは、Web会議システムを使用したオンラインセミナーとして開催します。
|
こちらのセミナーは受付を終了しました。
次回開催のお知らせや、類似セミナーに関する情報を希望される方は、以下よりお問合せ下さい。