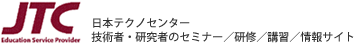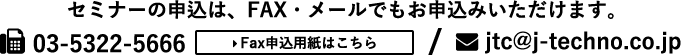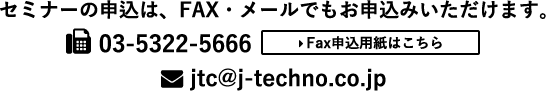ガス分離膜の設計・評価手法および水素・二酸化炭素分離への応用と実用化のポイント <オンラインセミナー>
~ シリカ系多孔膜の製膜法と細孔径評価手法、細孔構造を制御した膜によるガス分離、種々の素材による分離膜の特徴と作製方法、各種分離膜による水素分離/二酸化炭素分離への応用 ~
・SDGsにおけるキーテクノロジーのひとつである「膜分離」について基礎から実用化技術まで修得し、水素製造や二酸化炭素回収に応用するための講座
・各種分離膜の製膜法やガス分離に重要な細孔径の評価・制御手法から水素や二酸化炭素のガス分離プロセスまで修得し、製品の設計・開発に活かそう!
オンラインセミナーの詳細はこちら:
・WEB会議システムの使い方がご不明の方は弊社でご説明いたしますのでお気軽にご相談ください。
講師の言葉
(第一部)
地球レベルでの環境負荷が問題となる現在では、持続可能な社会を構築するためにどのような貢献ができるかが重要です。膜分離工学は、化学や医薬などすべての工業プロセスで重要な役割を果たし、水処理やCO2分離のような環境問題の解決においてもキーテクノロジーとなるため、国連が定めた、Sustainable Development Goals(SDGs、持続可能な開発目標)への貢献が大きい技術です。当研究室では、シリカ、チタニアなどの無機材料、および有機・無機ハイブリッド材料に着目し、製膜・評価技術の確立、透過・分離特性の検討を通じてあらゆる膜分離プロセスについて基礎から実用レベルの研究を行っています。
本講演では、膜分離のなかでガス分離を中心に、無機材料であるシリカ系多孔膜の製膜法、細孔径評価技術、透過装置の概要を中心に解説します。また、シリカ系多孔膜のサブナノレベルでの細孔構造制御法、各種ガス分離特性について最新の研究成果も含めて紹介します。
(第二部)
ガス分離法の実用化には十分な分離性能を持つガス分離膜が必要である。ガス分離膜の分離性能は、膜素材が持つガス分離性能だけでなく、欠陥のない大面積の薄膜への成形加工性にも大きな影響を受ける。得られる濃縮ガスの濃度が操作条件の影響も受けることはよく見落とされる事実である。圧力差を駆動力とするため、分離で得られる2つの濃縮ガスの一方は高圧、他方は低圧となる。従って、分離対象によってその有効性は異なる。水素分離は最初に実用化され、膜によるガス分離が有効である場合が多い。また、二酸化炭素も特定の用途で普及が進む。水素と二酸化炭素は低炭素社会の実現において重要なガスである。
本セミナーは、膜によるガス分離の基礎を、膜素材とプロセスの両方の観点から解説する。また、膜を用いたガス分離の分野における最近の話題についても紹介する。これにより、近年、注目されることが多い水素分離と二酸化炭素分離への膜分離の応用に関する話題を深く理解するために必要な基礎知識を提供する。
セミナー詳細
| 開催日時 |
- 2024年09月03日(火) 10:30 ~ 17:30
|
| 開催場所 |
オンラインセミナー |
| カテゴリー |
オンラインセミナー、電気・機械・メカトロ・設備、化学・環境・異物対策 |
| 受講対象者 |
・膜によるガス分離に興味のある技術者および材料研究者の方
・各種の化学プロセスや環境プロセスに従事されている方
|
| 予備知識 |
・大学レベルの一般化学の知識
・大学レベルの物理化学や化学工学の知識があると理解が深まるが、基礎から分かりやすく解説します
|
| 修得知識 |
・膜分離の基礎知識やその特徴
・細孔径評価技術(バブルポイント、ナノパームポロメトリー、ガス透過法)
・ガス分離膜の透過性評価手法(純ガス、混合ガス、水蒸気共存系)
・シリカ系多孔膜の技術背景・特徴
・シリカ系多孔膜の細孔径制御技術やガス分離特性の研究動向
・膜を用いたガス分離プロセスによる水素や二酸化炭素回収の実用技術
|
| プログラム |
|
第一部
1.膜分離の基礎
(1).化学プロセスにおける分離操作の重要性
(2).分離操作のあれこれ
(3).膜分離操作のメリット
(4).膜分離法の種類と分離対象
(5).代表的な膜材料と膜構造
2.シリカ系多孔膜の製膜法と細孔径評価
(1).ゾル-ゲル法によるシリカ多孔膜(ゾル調製、製膜法)
(2).細孔径評価技術(バブルポイント、ナノパームポロメトリー、ガス透過法)
a.バブルポイント法の原理
b.ナノパームポロメトリー法の原理、親疎水性評価
c.ガス透過法
・ガス性能評価:透過率と透過係数、トレードオフカーブ
・ガス透過率の測定:装置概要、透過率の算出法(擬定常、容積、sweep法)
・2成分混合ガス分離:分離予想線と分離限界線
・ガス透過および水蒸気透過実験
・溶存ガス、水蒸気透過実験
3.Modified Gas Translation (m-GT)modelによる細孔径の算出
(1).多孔膜における気体透過メカニズム
(2).気体透過率の分子径依存性によるサブナノ構造評価
(3).Normalized Knudsen-based Permeance(NKP)法の提案
a.規則性材料(ゼオライト)を用いたモデルの検証
b.気体選択性の予測
4.細孔構造を制御したシリカ系多孔膜によるガス分離
(1).代表的な水素分離系
(2).シリカ系多孔膜の技術背景・特徴
(3).シリカ系材料による水素分離膜の作製
a.水素分離:有機ハイドライド脱水素、アルカン脱水素系
・オルガノシリカによる細孔径制御:スペーサー法
・耐熱性オルガノシリカ構造設計
b.水素分離:メタン水蒸気改質,、アルコール改質系
・カチオン、アニオンドープによる細孔径制御
・Pd-SiO2 mixed-matrixによるH2親和性制御
(4).シリカ系多孔膜による二酸化炭素分離の作製
a.アミン系シリカによる細孔構造制御,表面改質(グラフト化)
b.第1~3級アミンの吸着力がCO2透過性に及ぼす影響
(5).シリカ系多孔膜の特徴、想定される分離対象
第二部 2.5h
1.素材の異なる分離膜の特徴と作製方法
(1).サイズの異なる孔
(2).孔のサイズとガス透過メカニズム
(3).膜素材の種類
(4).ガス透過性の比較
(5).高分子膜のガス透過分離性能
(6).炭素膜
(7).ゼオライト膜
2.水素分離への応用
(1).オフガスからの水素回収
(2).膜反応器
(3).光触媒水素製造への応用
3.二酸化炭素分離への応用
(1).天然ガスのメタン精製(CO2/CH4分離)
(2).バイオガスのメタン精製
(3).燃焼後の二酸化炭素回収
(4).燃焼前の二酸化炭素回収
(5).大気からの二酸化炭素の回収
|
|
| キーワード |
化学プロセス 膜分離法 ガス分離膜 シリカ系多孔膜 ガス透過 気体透過 細孔構造 水素製造 二酸化炭素回収 カーボンニュートラル SDGs 膜モジュール 高分子膜 無機膜 光触媒 天然ガス バイオガス メタン精製 |
| タグ |
エネルギー、リサイクル、エネルギーマネジメントシステム、ガス、化学工学、シール・ガスケット、環境、水素、吸着、スマートグリッド、空調、高分子、触媒、プラント、膜、自然エネルギー、自動車・輸送機、省エネ、設備、電源・インバータ・コンバータ、電装品、発電 |
| 受講料 |
一般 (1名):49,500円(税込)
同時複数申込の場合(1名):44,000円(税込)
|
| 会場 |
オンラインセミナー
本セミナーは、Web会議システムを使用したオンラインセミナーとして開催します。
|
こちらのセミナーは受付を終了しました。
次回開催のお知らせや、類似セミナーに関する情報を希望される方は、以下よりお問合せ下さい。