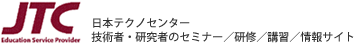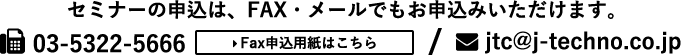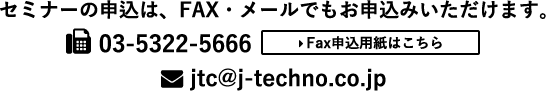センサ回路・センサ信号処理の基礎とセンサ回路設計への応用および注意点 <オンラインセミナー>
~ 各種センサの動作原理、センサからのデータ取り出し方法と信号処理回路、PSoCの活用法、センサ回路設計に関する注意点、IoTにおけるセンサ活用の工夫 ~
・センサ情報処理回路の設計とセンサからの複合的なデータ解析に活かすための講座!
・センサの種類と動作原理、信号処理回路技術、回路設計時の注意点を修得し、IoTデバイスやデータ解析を行う製品開発に必須である「センサ回路・センサ信号処理」の設計技術に活かそう!
オンラインセミナーの詳細はこちら:
・WEB会議システムの使い方がご不明の方は弊社でご説明いたしますのでお気軽にご相談ください。
講師の言葉
ここ数年急速に進展しているIoTですが、IoTでできること、できないことが、だいぶはっきりしてきました。このIoTを支える中心技術の1つは、まさにセンサ技術です。そして、センサからいかに情報を引き出して活用するかがポイントとなります。
本セミナーでは、何のために、どんな情報を、どのようにして取り出すか?そしてそれをどうIoTに活用するか、について幅広く学習していただきます。具体的には、まず、様々なセンサ(物理センサ・化学センサ・そその複合型)の動作原理、そしてそのセンサから情報を引き出すためのセンサ信号処理について講義します。特に、センサ情報処理については、アナログ情報処理とディジタル情報処理をどうバランスとって使っていくのかについて事例を交えながらご紹介します。次に、センサ情報回路を設計していく上での注意点について解説していきます。
最後に、実際にセンサ情報からどうデータ解析に繋いでいくか、そして長期動作における留意点について解説します。特にIoTで応用に成功している方法として、センサを元々の事象で使わず、違う事象で使うことで間接的に数値化していく方法があり、その事例について解説します。
セミナー詳細
| 開催日時 |
- 2024年07月09日(火) 10:30 ~ 17:30
|
| 開催場所 |
オンラインセミナー |
| カテゴリー |
オンラインセミナー、電気・機械・メカトロ・設備 |
| 受講対象者 |
・センサ・回路の研究開発に携わる技術者の方
・IoTシステムの開発に携わる技術者の方
・従来にないセンサ応用に携わる技術者の方
・センサ情報処理の研究開発に携わる技術者の方
|
| 予備知識 |
・上記の方であれば、特に必要ありません |
| 修得知識 |
・センサの動作原理・センサ回路・信号処理の基礎知識
・センサの意外な活用法とそれに基づくデータ分析の基礎知識
・基本的なセンサ信号処理とその使い方のポイント
・IoTシステムの設計や応用に亘る幅広い知見 |
| プログラム |
1.各種センサの動作原理
(1).センサの種類と用途
a.市販されているセンサ一覧
b.集積化センサ(MEMSなど)
(2).物理センサの動作原理と適用例
a.物理センサの動作原理(抵抗変化、容量変化)
b.応用例:ひずみセンサ、加速度センサ、温度センサ
(3).化学センサの動作原理と適用例
a.化学センサの動作原理(化学反応、吸着反応)
b.応用例:ガスセンサ、湿度センサ、アルコールセンサ
(4).物理と化学の複合型センサとその適用例
a.物理センサと化学センサの複合とは何か(化学反応を物理センサで読み取る)
b.応用例:生体センサ(グルコースセンサ)
2.センサからデータの取り出し方法と信号処理回路
(1).データの取り出し方について(電圧・電流・容量・発振周波数・位相差、など)
(2).一般的な信号処理の原理
a.A/Dコンバータによるアナログ/ディジタル変換
b.TDC(time to digital converter)による時間/ディジタル変換
c.アナログ増幅器(オペアンプ、ボルテージフォロワ、など)による信号増幅とインピーダンス変換
d.フィルタ処理(ローパス・ハイパス・バンドパスフィルタ、など)
e.変調信号による情報処理
(3).アナログ信号処理とディジタル信号処理の境目
a.どこまでアナログでどこからディジタルで処理すればいいか
b.アナログ回路とディジタル回路それぞれの役割
c.設計の際のポイント(アナログ回路・ディジタル回路の良さを使って、いかに補完関係になるように設計するか)
(4).ハードウェアをプログラマブルにできるマイコン(PSoC)の活用法
a.PSoCによるセンサ情報処理回路の設計
3.センサ回路設計に関する注意点
(1).注意しなければならないこと
a.電源・温度・外部等に起因するノイズ
b.周波数帯域からくるノイズ(1/f, KT/C)
b.入出力レンジ・帯域の重要性
c.温度ドリフト
d.インピーダンスミスマッチ(出力インピーダンスがあまり低くないセンサの対処法)
e.発振器等におけるノイズ(位相ノイズ)
(2).実際に動作させる際に気をつけるべきこと
a.電源の選択(電池・AC電源)
b.配線と部品の配置
c.発振動作(アナログ回路)
d.部品の選び方(接合型FET・MOSFET、受動素子)
4.センサの使い方の工夫と新たなIoT展開
(1).センサを仕様通りにつかう
a.具体例(温度計測、気圧計測、加速度計測)
(2).センサを仕様と少し違う使い方をする
a.人やものの状態を、センサを使って間接的に数値化する
b.具体例(空気清浄度、人の混み具合、高さ計測)
(3).複数の次元の違ったセンサ情報からの複合解析
a.複数の情報を扱うことの意義
b.次元の違うデータの揃え方
(4).少しちがう使い方によるIoTの実用
(5).IoTデバイス・サービスにおける長期動作(数年以上)に対する留意点
a.長期動作で必要な考え方(メンテナンス、データ収集、など)
b.気を付けておかないといけないこと(ハードウェアの製品サイクル)
|
| キーワード |
センサ 物理センサ 化学センサ 信号処理 変調信号 フィルタ処理 PSoC ノイズ 周波数帯域 インピーダンスミスマッチ 発振動作 |
| タグ |
信号処理、センサ、回路設計 |
| 受講料 |
一般 (1名):49,500円(税込)
同時複数申込の場合(1名):44,000円(税込)
|
| 会場 |
オンラインセミナー
本セミナーは、Web会議システムを使用したオンラインセミナーとして開催します。
|
こちらのセミナーは受付を終了しました。
次回開催のお知らせや、類似セミナーに関する情報を希望される方は、以下よりお問合せ下さい。