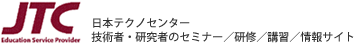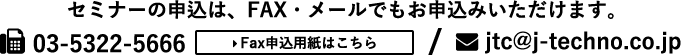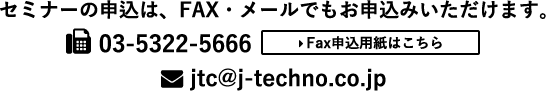機械設計者に必要な失敗事例・事故事例から学ぶ安全設計のポイントと実務への活かし方 【弊社研修室】
~ 「失敗」の重要性、整備不良/運転ミス/不正問題/加工硬化/温度差/熱処理/腐食/締結の失敗/高分子劣化などによる事故・失敗事例と具体的対策 ~
・機器の不具合による重大事故事例から、根本的原因の追究方法や設計段階でできる再発防止策立案の実践ノウハウを修得し、安全で信頼性の高い製品を開発するための講座
・機械製品の開発における失敗の分析と克服から講師が学び蓄積してきた実践的なノウハウや知見を修得し、技術者としてのスキルを向上しよう!
※書籍『機械設計失敗事典 99の事例から学ぶ正しい設計法』(ISBN:978-4-274-23339-5)を配布いたします
講師の言葉
商品開発には失敗が付きものです。部品が壊れたとき安易な補強で不具合の再発を経験したことは有りませんか?それは、根本原因に対処できていないからです。真の失敗を追究することこそが効率の良い対策方法です。そして真の原因追求は新しい技術(ノウハウ)を身に付け、会社及び技術者のレベルを上げることにもなるのです。
開発業務は精神的に厳しいが好きでなければ良い仕事ができません。大学での講師経験から、良い技術者を育てるには技術の面白さを知って貰わなければいけないと考え「機械設計の失敗事典」を執筆しました。このセミナーを受講されることで、「失敗事象の追究→ベストな対策→新ノウハウを得る→新技術が面白い→仕事が楽しい→より良い仕事ができる」の良い循環ができます。セミナー受講後には「一般に面白くないネガティブ不具合対策業務」をポジティブに考えて、楽しい仕事人生を送られるものと思います。
セミナー詳細
| 開催日時 |
- 2025年11月07日(金) 10:30 ~ 17:30
|
| 開催場所 |
日本テクノセンター研修室 |
| カテゴリー |
電気・機械・メカトロ・設備、品質・生産管理・ コスト・安全 |
| 受講対象者 |
・自動車、鉄道、航空宇宙、船舶、建設機械、昇降機などの機械製品に関連する設計開発者、製品評価技術者、運行管理技術者、整備管理技術者、事故調査技術者 など
・機械製品の不具合の原因と解決方法や未然防止策を修得したい方
・部下や後輩に技術指導をする立場にあり、実践的なノウハウを修得したい方
|
| 予備知識 |
・機械工学の基礎知識や機械製品に携わった経験 |
| 修得知識 |
・熟練技術者の経験から得られるノウハウ、頭で考える設計の落とし穴、「製品使用者や整備技術者がミスを起こさないための設計」を考える姿勢などを習得できます |
| プログラム |
|
1.失敗事例・事故事例から何を学ぶか
(1).複合的に重なるミスや失敗から真の原因を追究する「失敗学」の重要性
(2).講師の作成した『失敗事典』の構成と活用法
(3).不具合報道情報に対するアンテナ感度を向上し、他社事例を自社で起こさない
2.整備不良による失敗事例と対策
(1).不完全な整備による事故
・兆候、整備ミス、設計ミス、整備基準
(2).正規品ではない部品を使用したことによる事故
・部品管理、類似品を使わない、異状に気づく設計
3.製造者や運転者による失敗とその原因および対策
(1).電車の車台亀裂(脱線の危機)を異常音で発見した不具合
・工程変更の影響管理、作業指示、熱処理、定期検査、対策で応力集中
(2).降坂車両の横転死亡事故
・フェード現象の理解と実践、教育、高度な安全設計への考え方
4.不正問題を設計者が発見した場合の対処法
(1).大型車のタイヤ脱落で死亡事故(など多数の事例を紹介)
a.応力集中、ばらつき
b.隠蔽体質、失敗を吊し上げるパワハラ体質、会社の危機、コンプライアンス教育
5.加工硬化による失敗と対策
(1).加工硬化をしやすい材料
(2).ステンレスのプレス加工による亀裂発生
(3).銅ガスケットの使用上の注意
a.焼鈍し硬度指定をすること
b.整備時に再使用禁止の指示
6.温度差による失敗と対策
(1).寒地温度や摺動部の温度変化は検討が漏れしやすい
(2).熱処理による変形、焼き割れ、サブゼロ処理、残留応力の影響
7.キャビテーションと腐食の未然防止
(1).キャビテーションエロージョン
・水質と飽和水蒸気圧による影響
(2).イオン化傾向
(3).用途に適しためっきの種類
8.締結の失敗事例と対策
(1).ねじ部の限界はめあい長さ不足
(2).締付け座面の塗装によるゆるみ(被締結面は原則として塗装禁止)
(3).軟質ガスケットを挟む場合の締付順序及び密着締付の重要性
(4).塑性域回転角度法による失敗事例(塑性域回転角度法締付の基本)
(5).水素脆性破壊(高強度締付け部のボルト設計時の注意事項)
(6).作業順序や作業スペースを考慮した設計
(7).締付方向の指定(ボルトとナットで締める場合の向きなどの原則とその理由)
(8).締付順序(複数方向締付けなどの間合いの注意事項)
9.ゴムや樹脂部品などの高分子劣化によるトラブル未然防止策
(1).耐熱・耐薬品性(ゴムや樹脂部品は使用温度領域や薬品によって材質選びが大切)
(2).耐寒性
(3).寿命予測(金属と異なり必ず寿命があるので定期交換時期を予測し指定)
(4).電気劣化(ゴムでも通電被害があることを理解すること)
10.講師の長年の実務経験に基づく機械設計の総括
|
|
| キーワード |
機械設計 失敗事例 重大事故事例 原因究明 安全性 事故対策 事故防止 未然防止 再発防止 産業機械 整備マニュアル 作業基準書 整備不良 不正問題 締結構造 溶接不良 |
| タグ |
精密機器・情報機器、ヒューマンエラー、リスク管理、安全、ガス、業務改善、カム、検査、コントローラ、シール・ガスケット、環境、信頼性試験・故障解析、センサ、高分子、品質管理、金属材料、ねじ、未然防止、バルプ・ポンプ、FMEA・FTA・DRBFM、プラント、ロボット、熱処理、位置決め、疲労、応力解析、紙送り機構、機械、腐食・防食、機械要素、強度設計、工作機、構造物、最適化・応力解析、材料力学・有限要素法、軸受け、自動車・輸送機、車載機器・部品、振動・騒音、制御、設計・製図・CAD、設備、伝熱、熱設計、配管、歯車 |
| 受講料 |
一般 (1名):53,900円(税込)
同時複数申込の場合(1名):48,400円(税込)
|
| 会場 |
日本テクノセンター研修室
〒 163-0722 東京都新宿区西新宿2-7-1 新宿第一生命ビルディング(22階)
- JR「新宿駅」西口から徒歩10分
- 東京メトロ丸ノ内線「西新宿駅」から徒歩8分
- 都営大江戸線「都庁前駅」から徒歩5分
電話番号 : 03-5322-5888
FAX : 03-5322-5666
|
こちらのセミナーは受付を終了しました。
次回開催のお知らせや、類似セミナーに関する情報を希望される方は、以下よりお問合せ下さい。