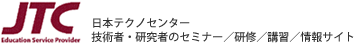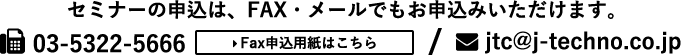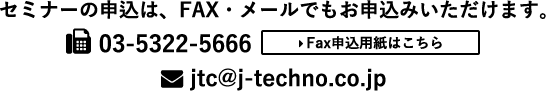疲労強度の基礎と疲労強度設計への活かし方および注意点とそのポイント <オンラインセミナー>
~ 破壊事故と原因、疲労強度設計の重要ポイント、疲労強度設計手法とそのノウハウ、製品開発や不具合対策の疲労強度設計への活かし方と注意点 ~
・機械製品や部品の疲労破壊防止策、問題未然防止策を学び、安全設計・強度設計に活かすための講座!
・実務経験豊富な講師から製品の破壊未然防止策の具体的な設計手法、疲労破壊の基礎と疲労寿命予測の有効な手法を修得し、疲労強度設計に活かそう!
・破壊の起こらない製品を設計するための疲労強度設計のノウハウと、具体的な疲労強度設計のやり方を実践的に修得し、実務での設計に活かそう!
オンラインセミナーの詳細はこちら:
・WEB会議システムの使い方がご不明の方は弊社でご説明いたしますのでお気軽にご相談ください。
講師の言葉
製品や部品などが破壊すると死亡事故やリコールなど重大事故につながります。今までの機械部品事故の原因をみると設計ミスが34%、使用環境条件の見誤りが26%で設計起因が60%、また、破損の原因は全体の78%が疲労破壊起因です。従って、機械関連の製品や部品の疲労破壊を発生させないための設計手法と問題を発生させない手法を設計者が良く理解していれば、この中の製品や部品などが破壊する重大事故を少なく出来ると考えています。
この研修では製品開発設計で講師が実践した製品の破壊を防ぐための具体的な設計手法をまず説明します。次に疲労破壊の基礎と疲労寿命予測の有効な手法を説明します。さらに講師が実践した事例を詳細に説明し、対話式の研修で、受講生の皆さんに設計実務を行う上で市場で破壊の起こらない製品を設計するための疲労強度設計のノウハウと、具体的な疲労強度設計のやり方を身につけ、実践力を習得して頂きたいと考えています。
セミナー詳細
| 開催日時 |
- 2025年12月01日(月) 10:30 ~ 17:30
|
| 開催場所 |
オンラインセミナー |
| カテゴリー |
オンラインセミナー、電気・機械・メカトロ・設備、加工・接着接合・材料 |
| 受講対象者 |
・構造体や機械部品、製品の生産に携わる開発、設計、品質保証、生産技術のエンジニアの方
・初級から中級のエンジニアの方
|
| 予備知識 |
・初歩の機械工学 |
| 修得知識 |
・製品、部品の破壊事故を防止するための手法
・製品寿命予測手法(S-N線図、疲労限度線図、応力拡大係数-き裂進展速度線図)
・疲労破壊のメカニズム
・具体的な疲労強度設計手法
|
| プログラム |
|
1.破壊事故と原因
(1).「空飛ぶタイヤ」の事故
(2).ハブ破損の原因
(3).破壊事故の原因
2.疲労強度設計の重要ポイント
(1).機械はなぜ、どのように壊れるのか?
(2).本講座で得られる強度設計の知識
(3).製品の破壊を防ぐには
a.要求仕様・使用環境条件の明確化
b.設計FMEAの活用
c.設計指針の活用
d.強度解析と実験の併用
e.許容応力と安全率の精度
f.製品構造体の材料の健全性と品質の確保
g.過去のトラブル事例集の活用
h.デザインレビューの活用
3. 疲労強度設計手法とそのノウハウ
(1).破壊形態
a.静的破壊
b.衝撃破壊
c.疲労破壊
d.クリープ破壊
e.遅れ破壊
(2).疲労破壊
a.機械材料の疲労
b.疲労のき裂
c.疲労破壊のき裂進展
(3).疲労寿命予測
a.S-N線図
・事例1:異種金属の溶接接合部疲労強度評価
・事例2:高圧燃料供給システムのエンドキャップ部の疲労強度評価
b.疲労限度線図
・事例3:ターボチャージャのタービン翼車設計
・演習1:高圧燃料システムの疲労強度評価
c.応力拡大係数とき裂進展速度(パリス則)
・事例4:タービン翼疲労破面からの応力推定
・事例5:燃料パイプとカップのロー付け接合部の破壊強度評価
・事例6:大陸間弾道ミサイルポラリスの開発
4. 製品開発や不具合対策の疲労強度設計への活かし方と注意点
(1).疲労強度設計フロー
・事例7:高圧燃料供給システムのプレート変形対策
(2).疲労強度設計で注意すべきこと
・事例8:高圧配管を取り付けた時に発生する応力
|
|
| キーワード |
疲労強度設計 破壊事故 疲労破壊のメカニズム 設計FMEA 許容応力 破壊形態 静的破壊 衝撃破壊 疲労破壊 クリープ破壊 遅れ破壊 き裂 応力拡大係数 き裂進展速度 パリス則 疲労限度 |
| タグ |
金属材料、ねじ、FMEA・FTA・DRBFM、ロボット、破面解析、疲労、機械、機械要素、強度設計、工作機、構造物、最適化・応力解析、材料力学・有限要素法、設計・製図・CAD、歯車 |
| 受講料 |
一般 (1名):49,500円(税込)
同時複数申込の場合(1名):44,000円(税込)
|
| 会場 |
オンラインセミナー
本セミナーは、Web会議システムを使用したオンラインセミナーとして開催します。
|
こちらのセミナーは受付を終了しました。
次回開催のお知らせや、類似セミナーに関する情報を希望される方は、以下よりお問合せ下さい。